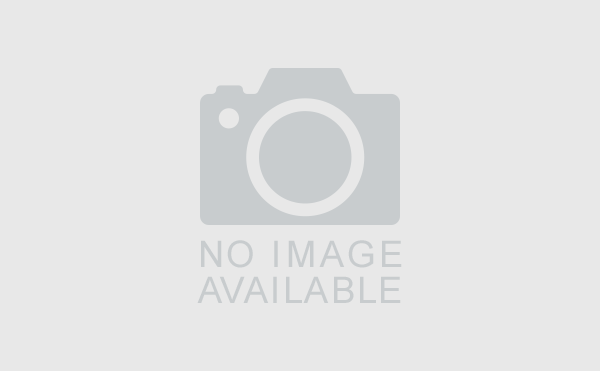信仰者の選択①狭い門か?大きな門か?(マタイの福音書7章13~14節)
1 はじめに
山上の説教は7章12節までで主要な教えを終え、13節以降は「その教えをどう生きるか」という選択を迫る部分に入ります。最初に示されるのが「狭い門に入れ」という呼びかけです。ここでいう「狭い門」は、入試などで使われる比喩とは違い、人間の力では入ることのできない門を指しています。大きな門は滅びに通じ、多くの人がそこを通りますが、狭い門はいのちに至る道につながり、見いだす人はわずかです。イエスさまは信仰者に向かって、どのような歩みを選ぶのか根本姿勢を問いかけています。
2 狭い門から入るとは
大きな門から入る生き方は、自分の栄光を求める道です。自分の思い通りに生き、自分の力を頼み、人や神への愛がありません。信仰を持ちながらもその延長線上に生きる人は少なくありませんが、その道は滅びに至ります。対して狭い門から入る生き方は、神の栄光を求める道です。神の御心に従い、神に頼り、神と人を愛する生き方です。弱々しく見え、好む人は少ないですが、この門は命の道に通じます。山上の説教はまさにこの道へ導くために語られました。イエスさまは愛をもって「狭い門から入りなさい」と呼びかけ、今決断するよう迫られます。
3 狭い門から入る者の生き方
狭い門から入る決意をした人には、神が「問題は自分自身にある」と示されます。キャサリン・マーシャルの『愛はいずこに』に描かれているエドは、自分の立場を利用し、一線を越えない程度に若い女性と親しくし楽しむという罪を暴かれました。その結果、母親を犯罪者にしてしまうという痛い経験を通して悔い改めに導かれました。具体出来事を通して罪が示され、悔い改めてイエスさまのもとに行くとき、閉じていた門が開かれます。私たちが通るべき門はイエスさまご自身だからです。イエスさまは「わたしは門です。わたしを通って入るなら救われます」(ヨハネ10:9)と語られました。この門は自分を捨てなければ入れません。しかし、十字架で私たちの代わりに死なれたイエスさまを信じる者は通ることができます。
4 細い道を歩むとは
さらにイエスさまは、門から入った後の道をも示されます。広い道は滅びに至りますが、狭い門を通った者は命に至る細い道を歩み始めます。山上の説教が教える「敵を愛せ」「姦淫するな」「さばくな」などの歩みを実践しようとすると、かえって自分の罪が明らかにされます。悔い改めに導かれます。それは、細い道を歩む者の体験です。イエスさまは「わたしが道であり、真理であり、いのちです」(ヨハネ14:6)と語られました。悔い改めてはキリストに戻り、また悔い改めては戻るという繰り返しこそ細い道です。何度失敗しても戻れるのは十字架が立っているからであり、その歩みの中で神の聖さと自分の罪深さに気づき、十字架がますます大きくなっていきます。
私たちは礼拝を欠かさずささげます。神の栄光をあがめるだけでなく、細い道から外れやすい弱さを知っているからです。御言葉によって再び細い道に戻していただく必要があります。互いに励まし合う群れが必要です。狭い門と細い道は確かに狭く細いですが、イエスさまが十字架で備え、何度も戻ることのできる道です。そこは平安と感謝、永遠のいのち、復活の希望の道でもあります。
5 おわりに
神の栄光を求める狭い門から入り、自分に死んで日々十字架に付けていく細い道を歩む者は幸いです。それはいのちの道、父なる神に向かう道です。「いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう」(マタイ7:14)。このイエスさまの言葉を真摯に受け取りましょう。そして、私たち自身に「あなたは狭い門から入り、日々自分を十字架に付けて歩んでいるか」と問いかけましょう。
(2025年9月7日 石原 俊一 師)