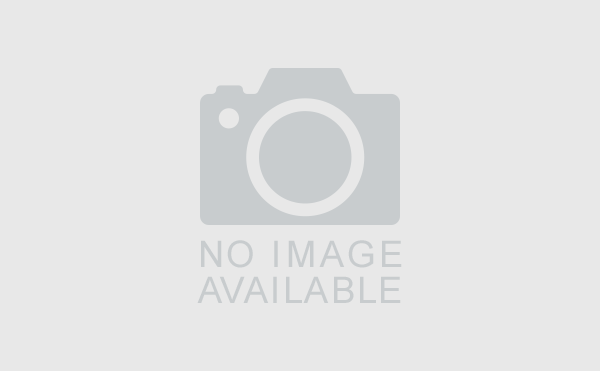さあ、主の家に行こう(詩篇122篇1~9節)
1 はじめに
詩人は長い旅の末、ついに目的地エルサレムに到着しました。詩篇122篇は「主の家」を中心に、「行く喜び」「そのすばらしさ」「平和の祈り」という三つの主題を語ります。旧約時代、主の家はエルサレムの神殿でしたが、今日の私たちにとっては教会であり、やがて完成する天の御国をも指します。
2 「主の家」に行く喜び(1–2節)
「さあ 主の家に行こう。」この呼びかけを聞いたとき、詩人は喜びに満たされました。神さまと出会い、交わることが最高の幸いだったのです。彼はいま、エルサレムの門の中に立ち、感動のあまり立ち尽くします。
私たちも同じです。誰かの「さあ、主の家に行こう」という誘いによって教会に導かれました。最初はためらいがあっても、やがて神さまの臨在の中で真の喜びと平安を経験します。
アウグスティヌスは「私たちの心は神のうちに憩うまで安らぐことはない」と言いました。主の家こそ、心の平安の源です。教会に集う喜びを思い起こし、神に立ち返るとき、再び平安が与えられます。
さらにこの詩篇は、天の御国をも指し示します。殉教者シュックは火刑の中で「さあ主の家に行こう」と歌いながら天の門へと入っていきました。信仰者の死は、永遠の主の家への旅立ちでもあるのです。
3 「主の家」のすばらしさ(3–5節)
詩人は、都エルサレムのすばらしさを三つに語ります。
① 一つにまとまっている都(統一性)
「一つによくまとまった都」とあるように、神の家は堅く結ばれています。教会もキリストにあって一つの体、神の家族です。信仰によって結ばれた一致がそこにあります。
② 多くの部族が上がる都(多様性)
エルサレムには多くの部族が集まり、共に神を賛美しました。教会も年齢・性格・背景の異なる人々が集い、赦し合い愛し合う場所です。統一性と多様性が共存するのが主の家の特徴です。
③ さばきの座のある都(問題解決の場)
ダビデ王朝の王座は正義の象徴でした。神の御前で罪が裁かれ、赦しが与えられ、問題が解決されました。教会もまた、神の前で悔い改めと赦しを経験し、心の平安を得る場所です。
地上の教会は不完全ですが、完全な主の家――天の御国では、統一・多様性・平安が完全に実現します。そこに向かう希望をもって、今ここで主を賛美し続けましょう。
4 「主の家」の平和の祈り(6–9節)
詩人は「エルサレムの平和のために祈れ」と呼びかけます。エルサレムとは「平和の都」という意味。神の支配を受けるとき、真の平安(シャローム)が実現します。彼は「あなたを愛する人々が安らかであるように」「あなたのうちに平和があるように」と祈ります。
私たちも教会と兄弟姉妹の平和のために祈るべきです。教会の平和が失われるのは、礼拝の信仰が失われ、人が自分の思いを優先するときです。礼拝とは、神の御前にへりくだり、御言葉に従う告白です。私たちが神の支配に生きるとき、教会に真の平和が保たれます。
だからこそ私たちは祈ります。「あなたの城壁の内に平和があるように。あなたの宮殿の内が平穏であるように。」互いのために祈り合い、キリストの平和が教会に満ちるように求めましょう。
5 終わりに
エペソ2:14は語ります。「キリストこそ私たちの平和です。隔ての壁を打ち壊された。」主イエスが十字架で流された血こそ、神と人、人と人との和解を実現する真の平和の源です。私たちは、この詩人のように「さあ、主の家に行こう」と喜びをもって歩みましょう。教会における一致と平和を守りつつ、やがて天の御国の門の内に立つ日を待ち望みましょう。
(2025年11月2日 石原 俊一 師)