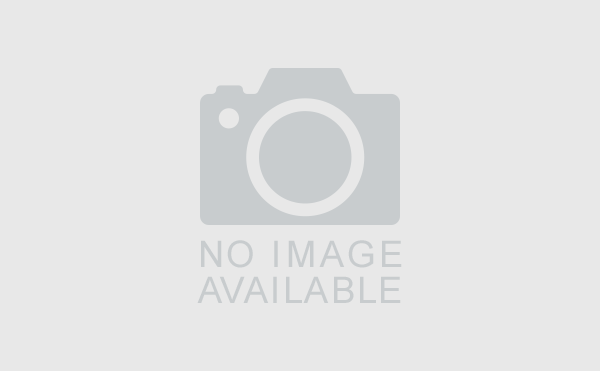真の弟子となるために(マタイの福音書8章18~22節)
1 はじめに
マタイの福音書8~9章に見られる、イエス・キリストの支配が広がる様子と、多様な人々がイエス様に従う姿を背景に、本説教では、イエス様に従うことを妨げる二つの大きな課題に焦点を当て、イエス様からの愛ある助言を通して「真に従うこと」の意義を明らかにします。
2 イエスに従うことを妨げるもの①:自分の信仰への自信
最初に登場するのは、一人の律法学者です。彼は聖書学者として高い知識と自信を持っていました。彼がイエス様に「先生。あなたがどこに行かれても、私はついて行きます。」(19節)と宣言した言葉には、「自分は立派な信仰者であり、どこまでもついて行ける」という自分の信仰に対する自信が表れています。しかし、イエス様は彼の期待とは異なる答えを返されました。これは、「私には寝る場所もない」という、イエス様の現実を示す言葉であり、律法学者の自己認識を深く考えさせることを意図しています。
イエスさまに従おうとするとき、まず見えてくるのは、パウロがローマ人への手紙で告白したような「善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理」であり、自分の自己中心や罪深さです。真の信仰は、勢いや自信ではなく、そのような惨めな自分を救ってくださったイエス・キリストの恵みに対する感謝から生まれます。律法学者の言葉は、この自己認識が欠けているために浅薄なものとなっていました。イエス様が歩まれたのは、人々に拒絶され、十字架にかかる「枕するところもない」道、すなわち、自己への自信が徹底的に打ち砕かれる道です。真の弟子となるには、この自信を捨て、それでも愛してくださるイエス様にただついていくことが必要なのです。
3 イエスに従うことを妨げるもの②:信仰の後回し
次に登場する一人の弟子の課題は、「信仰の後回し」でした。彼はイエス様に、「主よ。まず行って父を葬ることをお許しください。」と申し出ました。律法にかなう常識的な願いに見えますが、「まず行って…」という言葉に、イエス様に従うことと、当時1年間を要したとされる父の葬儀(親孝行)を天秤にかけ、信仰の優先順位を下げた姿勢が見られます。イエス様は、「何よりも大切なことは、イエス様に従うことであり、このことを後回しにしてはいけない」と告げられました。イエス様に従う者の大切な働きは、いのちを与えることです。イエス様は、死んだ者を葬る行為(すなわち、信仰をもたない者にもできること)よりも、罪に死んでいる者に永遠のいのちを与えるという、ご自身の働きと弟子の役割の重要性を強調されました。
信仰をこの世の事柄と天秤にかけ、後回しにすることは望ましい姿ではありません。例えば、「子どもを立派に育てる」ことを目標にし、信仰をそのための手段とする母親の例に見られるように、何かを「まず」と置いて、信仰を後回しにするとき、神様が与えようとしておられる祝福を受け損なってしまいます。イエス様は、まずイエス様に従うことを第一にすれば、父の葬儀(課題)に対しても、神様の御栄光を現す最善の導きが与えられることを伝えたかったのです。真のキリスト者は、まずキリストに従い、その中で目の前の課題を信仰によって解決していきます。
4 おわりに -今日の愛の助言-
真の弟子となることを妨げる二つの課題、「自分の信仰への自信」と「信仰の後回し」の根本は、自分の思いへの執着、すなわち、自分に死ねないことです。幸いなことに、この二人は課題を抱えながらもイエス様のもとに行き、愛の助言を受けました。群衆のように遠ざかるのではなく、イエス様のもとに行けば、必ず導きがあります。
イエス様は今日も「まず、わたしに従いなさい。」と語られます。あなたの心の中で、イエス様より「まず」と置いてしまっている偶像を打ち砕き、「ただ、あなたに従います」と応答するとき、イエス様の真の弟子となるための祝福の道が開かれるのです。
(2025年11月23日 石原 俊一 師)