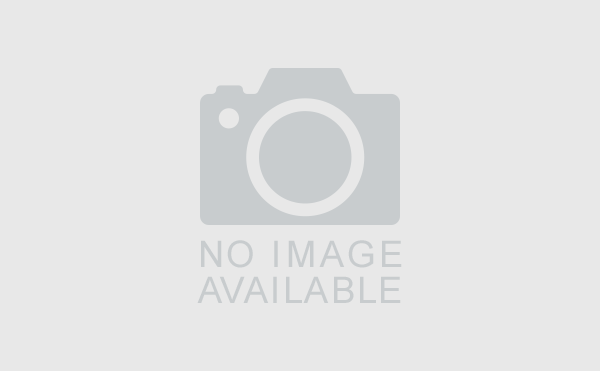律法の真意3「誓ってはならない」(マタイの福音書5章33~37節)
1 旧約聖書にかかれている「誓い」
誓いとは、「誓いとは、自分の言葉の真実性を保証するために、あるものを根拠として宣言すること」です。
神さまは誠実なおかたです。ですから神さまは自らの誓約を必ず実現してこられました。(ヘブル人の手紙6:13-15、Ⅱコリント1:19-20)その神さまは、人にも「誓い」を果たすように求めてこられました。『偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせ』(5章33節)と語ったとおり、旧約聖書では、レビ記19:12、民数記30:2などによって、神さまは、神と人とに誓いを果たし、誠実に生きるように求めておられます。
2 イエスさまの時代の人々の過ち
しかし、イエスさまの時代の人々は、自分達で決まりをつくって、自分達が律法を守っていることを保証しようとしました。その結果生み出されたのが。誓いのランク付けです。何にかけて誓うかによって、誓いの-ランクをつくったのです。絶対に守らなければ成らないのはAランクはである「神の名」による誓いです。Bランク「天にかけて」「地にかけて」「エルサレムにかけて」「神殿にかけて」、Cランク「祭壇にかけて」「供え物にかけて」Dランク「頭にかけて」とレベルが下がれば下がるほど誓いをはたさなくてもよいという決まりでした。このようなランク付けによって、彼らは、誓いを果たさなくても自分が律法を守る立派な人間だと示そうとしました。
3 イエスさまが示す律法の真意
イエスさまは、彼らはこれらのランク付けに反論します。地、天、エルサレムそして、頭も神の毛も、すべて神さまの御支配の中にあります。ですから、何にかけて誓ったとしても「神さまにかけて誓うこと」と同じです。誓ったら必ずその誓いを果たさなければなりません。イエスさまは、はじめから抜け道を想定するような誓いは決してしていけないと説くのです。
4 「誓うな」について
山上の説教は、人は御言葉に従って歩むことができないということを示してきました。自分自身の罪や弱さを自覚するとき、人はとても「誓い」を立てることのできる者ではないことが分かってきます。
パリサイ人や律法学者は自分の罪や弱さが分かりませんでした。そして、自分がいかにも律法を守る立派な者であることを示すために不誠実な「誓い」を繰り返しました。しかし、神さまの前に立ち、御言葉を真摯に受け容れる者は、自分の弱さを認め、イエスさまに寄りすがることしかできません。
5 「はい」は「はい」、「いいえ」は「いいえ」
ですから、イエスさまは、「目の前のことを受け容れることができるなら、「はい」という。受け容れられないなら「いいえ」といいなさい。」と命じます私たちは、日々神さまの導きの中で生きています。その歩みの中で、これは神さまの導きと信じ受け容れたときは、「はい」といって歩み出します。そして、もし、神さまの、導きを受け容れることのでいないときは、「いいえ」と神さまに祈って、神さまの導きを受けていきます。神さまは、「いいえ」と神さまに祈る者を導いてくださいます。ときには、「いいえ」という祈りを「はい」に変えられることがあります。ときには、「いいえ」のまま歩み出しなさいと導かれることがあります。大切な事は、自分のありのままの気持を神さまに祈り、神さまの導きを受けていくことです。誓う必要はありません。自分を立派に見せる必要はありません。イエスさまは、私たちが自分を偽らなくても、私たちの真実の姿をご存知だからです。
6 「それ以上のこと」
イエスさまは、「それ以上のことは悪い者から出ているのです。」とお語りになりました。「はい」「いいえ」と誠実に神さまに祈り、神さまに導かれる以上のことは、自分の思いを押し通したかったり、自分をより良く見せたかったりすることです。「悪い者から出ている」と訳されていますが、原語は「悪から」となっています。そして、「悪い者から」からの「から」の原語は、「中から外へ」という意味があります。つまり、「それ以上こと」、神さまの御心に沿わない思いは、人の心の内から出てくる思いです。人の悪の心が、神さまに導かれることを拒否する心が人の心の内側から外に出て行くのです。
しかし、イエスさまが私たちに求めておられるのは、ありのままで神さまの導きを受けていく心です。私たちは、誠実に神さまに従っていきたいと願います。
(2025年3月30日 石原 俊一 師)