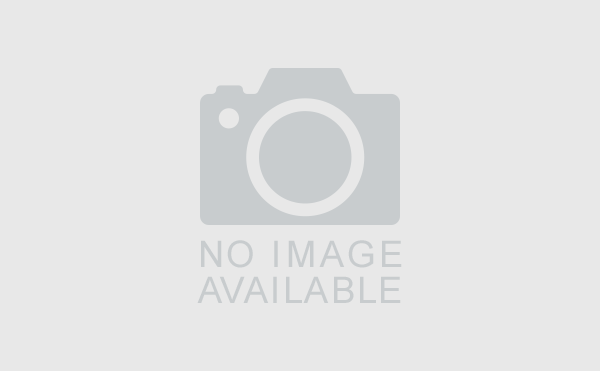律法の真意4「悪い者に手向かうな」(マタイの福音書5章38~42節)
1 「目には目を、歯には歯を」
イエスさまは、「『目には目を、歯には歯を』と言われていたのを、あなたがたは聞いています。」 (38)と語られました。出エジプト21:22-25には、「償わなければならない」と書いてあります。人間は、被害に遭うと、どうしても被害にあった以上の報復をしたくなります。しかし、報復を受けた者は、それ以上の報告をしたくなります。このような報復の悪循環をふせぐために、加害者が、「目に対して目、歯に対して歯の補償をすることが律法に定められているのです。
2 悪い者に手向かってはいけません
イエスさまは、「悪い者に手向かってはいけません」(39)と語られたのには二つの理由があります。
一つ目の理由は、被害者の心は、「やられた」ことで煮えくりかえる怒りをもつからです。たとえ、お金で保障されたとしても、被害者は簡単には加害者を赦すことができません。それでは、心の中の「報復の悪循環」はなくなりません。そこで、イエスさまは、被害者に加害者に立ちむかわず、加害者を愛することで「報復の悪循環」を「愛の好循環」に変えるように求められたのです。
二つ目の理由は、私たちは、これまで、山上の説教をとおして自分は律法に死んだ罪人であることを認めてきたからです。悪い者に手向かおうという気持は、人の自尊心から生まれてきます。しかし、イエスさまは、律法に死んだ者は、悪い者手向かう心もまた死んでいるはずだと語られるのです。
3 悪人に手向かわない4つの事例
私たちは、律法に死んだはずなのに、悪い者に立ちむかう心が生きています。イエスさまは4つの事例をとおして、その自我を浮き彫りにします。
一つ目の例が、あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けることです。(39)右利きの人が右の頬を打つということは、右の手の甲で「ペチン」と打つということです。相手は自分を馬鹿にしています。そのとき、イエスさまの命令は、「左の頬も向けなさい。」というのです。
二つ目の具体例は、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着も取らせなさい。(40)です。当時上着は、防寒具や寝具としても使われていました。上着は、その人のいのちにかかわる大切な着物として上着は人に取られないように律法が守っていました。ところが、イエスさまは、下着を取ろうとする者には、上着という自分の生きる権利をも与えてしまえと言うのです。
三つ目の具体例は、「あなたに一ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に二ミリオン行きなさい。」(41)です。当時はメールはもちろん郵便の制度もありません。ローマ国王は、出来るだけ早く情報を送るために飛脚を飛ばしました。そして、いつでも飛脚が活用出来るように、当時の民に手紙を運ばせたり、飛脚のために、必要な馬などを供出させたりしました。だれでも、強いていかされることはいやがります。しかし、イエスさまは、「あなたに一ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に二ミリオン行きなさい。」と語られました。
四つめの具体例は、「求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。」(42)です。原語は、「求める者にあなたを与えなさい。」と、「あなた」という言葉があります。自分に死んでいる人は、一切を神さまにゆだねて自分を与えることができるというのです。
4 御言葉に歩んでくださるイエスさま
私たちは、四つの具体例から人との関わりの中で、自分を捨てることができない者であること、死んだはずの自我が生きていることを思い知らされます。そのとき、聖霊は「悪い者」(39)が私であることを示してくださいます。しかし、イエスさまは、「悪い者」である私に立ち向かわず十字架にかかって死んでくださいました。
私たちは、御言葉に歩めないそのありのままの姿をイエス様の十字架につけるしかありません。イエスさまの十字架によって、イエスさまと私が一つとなります。イエスさまが私の罪を引き受けてくださいます。そして、イエスさまが、イエスさまのいのちを私に与えてくださいます。そのとき、イエスさまが語られる御言葉が私のうちにアーメンとなります。私をとおして、報復の悪循環が愛の好循環に変えられるのです。
私の内に生きてくださるイエスさまがイエスさまのご命令を実現させてくださることを祈りましょう。この世では完全に御言葉通り歩むことが出来ないかも知れませんが、やがて来る愛と平安に満ちた神の国は愛の好循環に満ちています。
(2025年4月6日 石原 俊一 師)